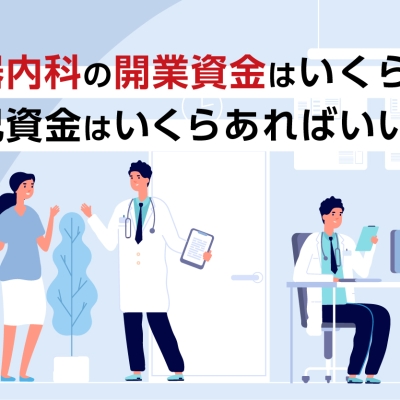消化器内科の開業資金はいくら必要?自己資金はいくらあればいいの?

消化器内科クリニックの開業にはどれくらいの資金がかかるでしょうか?
消化器内科クリニックは、内視鏡カメラが必要となることから機器の費用が膨らむ傾向にあります。何本内視鏡カメラを準備するかによっても必要な費用が異なってくるでしょう。
今回は消化器内科クリニックの開業資金や、必要な自己資金、開業成功のポイントについてご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
まずは、私の自己紹介をします。プラザ薬局の医院開業担当をしている田中と申します。
元々医療器機ディーラーで17年務めており、この間に内科ドクター2名、整形外科ドクター6名の開業支援を経験しました。その後、ドクターの開業コンサルティング業務をメインに行うようになり、医療モールの組成も行うようになりました。その間、内科5名、皮膚科2名、小児科4名、整形外科6名、心療内科2名、眼科1名、継承開業にて内科2名の開業を支援しました。そのほか、ドラッグストア併設のクリニック誘致も行っています。
このように、様々な診療科の開業支援、そして医療モールの組成を行い、成功に導いてきました。これまでの経験をもとに、医療モールで開業を検討中のドクターの皆さんに少しでも役立つ情報をお伝えできればと思います。
消化器内科の開業資金はいくら必要?
消化器内科の開業資金はクリニックの面積によって大きく異なりますが、1億1,000万〜1億4000万円程度となり、比較的高い金額であるといえます。
50坪のクリニックと仮定した場合の開業費用について、ざっと内訳の例をご紹介すると、以下のようになります。
|
建築関係(4500万円程度) |
|
|---|---|
| 内装費用 | 4000万 |
| 看板費用 | 150万 |
| 設計費 | 200万 |
| +賃料 | |
|
創業費用(3000万円程度) |
|
|---|---|
| 不動産仲介手数料 | 賃料の1か月分 |
|
行事費用 |
200万円 |
| 保証金 | 賃料の6か月分から12か月分 |
| 医師会入会金 | 450万円(大阪市の場合) |
| 開業時運転資金 | 2000万円 |
|
器機、什器、備品など (3500万円程度) |
|
|---|---|
| 電子カルテ(5台構成) | 400万円 |
|
内視鏡、洗浄機、X線、PACSなど |
2700万円 |
| 予約システム、検査機器など | 400万円 |
|
什器 |
200万円 |
| その他備品 (鋼製小物など多々) |
150万円 |
| 自動釣銭機 | 150万円 |
一部では、内装費用を坪単価60万円前後で計画を立てるケースも見受けられますが、実際の施工段階では設計変更や設備追加により、結果的に大幅なコスト増に繋がることも珍しくありません。したがって、初期の見積もりが坪単価80万円を下回る場合には、その算出根拠や今後想定される費用変動の可能性について、慎重な確認が必要です。
加えて、施工業者の選定や仕上げに対するこだわりの度合いに応じて、一定のコスト調整は可能ではあるものの、医療機器の調達費用も見逃せない負担要因となっています。特に海外メーカー製品が中心となる診療科においては、円安の影響を強く受けており、価格上昇が顕著です。たとえば、消化器内科における内視鏡システムは高額機器の代表であり1台2000万円程度します。複数台を整備しようとすれば、初期投資が想定を大きく上回ることも十分にあり得ます。
自己資金はいくらが妥当?
開業資金と聞くと、「全額を自己資金で用意しなければならないのでは」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、開業資金のすべてを自己資金で賄う必要はありません。一般的には、総額の約1割程度を目安に自己資金を準備しておくケースが多く見受けられます。たとえば、開業資金が1億1,000万円であれば自己資金は1,100万円、1億4000万円であれば1,400万円程度が目安となります。
なお、実際の運用においては、自己資金を直接使用しない場合も少なくありません。特に個人事業として開業する場合、開業にかかる費用は個人口座から支払われることが一般的であるため、自己資金と開業資金の区別があいまいになる傾向があります。そのため、「必要なタイミングで支払いができる体制を整えておく」ことが重要となります。具体的には、物件取得時の保証金や仲介手数料など、融資実行前に発生する初期費用が代表的です。また、金融機関からの融資を受ける際に、一定の自己資金を確保していることが信用の裏付けとなる場合もあります。
事前に無理のない範囲で自己資金を準備しておくことが、スムーズな開業につながるでしょう。
足りない部分はどう資金調達する?
自己資金以外の開業資金については、通常、金融機関からの事業融資を活用するのが基本的な調達手段となります。自己資金は、開業前に必要となる諸費用(例:物件契約時の敷金や保証金、仲介手数料など)に充てる「先行支払い用の資金」として重要な役割を果たします。
しかし、開業準備の段階では、融資が実行される前に多くの費用が発生するため、手元資金だけでは対応が難しいケースもあります。そうした場合には、「つなぎ融資(ブリッジローン)」の活用が有効な手段となります。これは、本融資の実行前に一時的に必要な資金を補う短期融資で、不動産購入時によく利用されています。クリニックの開業においても、資金繰りに柔軟性を持たせる方法として検討する価値があります。
資金調達の際、自己資金が潤沢にある場合でも、それをすべて開業資金に投入するのが必ずしもベストとは限りません。現在の低金利環境では、金融機関からの融資を適切に活用することで、資金効率を高めながら、予備資金を確保し、将来的な経営の柔軟性を維持することが可能です。また、金融機関は融資審査の際、自己資金比率や資金計画の妥当性だけでなく、事業計画の実現可能性や収支予測、運転資金の余裕なども重視します。単に借入額を抑えることよりも、事業としての持続性とリスク管理がしっかりされているかが評価のポイントとなります。
開業後に資金が不足するケースの多くは、開業前の資金計画が不十分であったことに起因します。開業直後は収益が安定せず、支出が先行するため、運転資金に余裕を持たせておかないと、資金ショートを起こす可能性があります。資金ショートを回避するには、初期段階で綿密なキャッシュフロー計画を立て、複数のシナリオを想定したリスク分析を行うことが重要です。また、一度融資を受けた後に追加融資を依頼する場合には、審査や手続きに時間がかかるため、経営計画そのものに支障をきたすことも考えられます。
親や親族から資金を借りることも可能ではありますが、そのお金が実質的に「贈与」とみなされた場合、贈与税が発生するリスクがあります。そのため、親族間での資金移動については、契約書の作成や返済計画の明確化など、税務リスクへの配慮が不可欠です。税理士など専門家の助言を得ながら進めるのが望ましいといえます。
また、設備投資に関しては、必要最低限の範囲でスタートし、経営の安定や患者数の増加に応じて段階的に拡充するという考え方が有効です。特に高額な医療機器については、購入ではなくリース契約を選択することで、初期費用を抑えつつ資金繰りに柔軟性を持たせることができます。リースは税務上のメリットもあるため、経営戦略としても一考の価値があります。例えば、消化器内科で使用する内視鏡検査機器は非常に高価ですが、開業時に複数本を揃えるのではなく、患者のニーズを見ながら段階的に追加導入するという判断も可能です。よく例え話で、ラーメン屋の話をします。ラーメン屋を開業するとなったとして、どれくらい来客があるかのわからないうちにラーメン鉢100個は必要なく、客が増加してきたタイミングで追加購入する人がほとんどだと思います。医療機器は日進月歩です。バージョンアップするタイミングに合わせて器機の追加購入を行うなど、開業当初は、必要最低限の機器購入にとどめ、患者数や検査ニーズが一定の水準に達したタイミングで設備を拡充する方が、資金効率の面でもリスク管理の面でも合理的といえるでしょう。
消化器内科の開業が成功するのに重要なポイントとは?
クリニック開業の成否を大きく左右する要素の一つが「立地選び」です。これは消化器内科に限らず、すべての診療科に共通する重要な検討ポイントといえるでしょう。特に、駅からの通勤・通学路やスーパーなど日常の買い物をする時に通る道のような生活動線上にあるのかということや、建物や看板の視認性の高さなどがスムーズな集患に大きな影響を与えます。クリニックの開業をいち早く知ってもらうことができれば、早期に地域に根付く可能性が高まります。
消化器内科の開業においてはエリアの選定も重要です。消化器内科では、胃カメラや大腸カメラなどを使った検査を保険診療外で実施するケースも多いです。保険診療外での検査は高額となりますので、ある程度生活に余裕があり、健康に対する高い意識を持っている場合でなければ定期的な利用は困難です。エリアによって、健康診断や人間ドックの利用率に差がありますので、こうした点を意識してエリアを選定することが一つのポイントとなるでしょう。競合がどれくらいいるのかという観点も外せない検討要素です。半径500m以内に競合があると厳しい戦いを強いられる可能性が高くなります。
専門コンサルタントが伝える成功パターンと失敗パターン
この章では、消化器内科のクリニック開業における成功パターンや失敗パターンについてご紹介します。
成功パターン
- 検査だけではなく一般内科診療にも力を入れている
消化器内科では胃カメラや大腸カメラを使った検査を行うケースが多いですが、当然、一般内科診療も実施しています。普段から一般内科診療にも力を入れて、地域住民のかかりつけ医となることに注力している医師がいるクリニックは成功しやすいです。内視鏡検査の診療報酬に偏ると、競合医療機関が近隣に開院した場合、内視鏡検査が減少した打撃が大きくなると思います。まずは地域のかかりつけ医として認知が広がると、例えば人間ドックを受診して再検査となった場合など、こうしたかかりつけの消化器内科を利用することとなり、自ずと検査利用の患者も増加することになるのです。効率的な検査を実施してくれる消化器内科も単発的な利用者によって盛業する可能性は十分にありますが、地域のために、患者のためにという思いを持ったクリニックは、長く地域に根付き、長期的な成功につながるでしょう。
- 検査に特化する場合は、駅前や駅近に開業する
検査に特化したいと考えているクリニックであれば、駅前や駅近に開業することが成功のキーポイントとなります。内視鏡カメラの検査は麻酔なしで実施することはできますが、患者さんが大きな苦痛を感じるケースも多々あり、麻酔を使用しての検査実施が増加しています。麻酔を使用した後は、公共交通機関を使用されるケースが多いです。そのため、車を使わずアクセスしやすい駅前や駅近のクリニックに患者が集まりやすくなるのです。
失敗パターン
- 医師のマネジメントスキルが不足している
消化器内科に限ったことではありませんが、クリニックを開業した後にマネジメントに苦労する先生は少なくありません。勤務医の場合は、自分だけでマネジメントを行うわけではありませんし、立場によっては患者にだけ向き合っていればよいという環境であったケースもあります。しかし、自身のクリニックを開業した場合においては、自分がリーダーとなってチームをまとめていくことが求められます。このマネジメントがうまくいかなければ、スタッフの早期離職につながったり、院内の雰囲気が悪化したりといった悪循環が生まれ、クリニックから人が離れていくリスクがあります。
- 診療時間が短い、診察終了時間が早いために患者が増えない
消化器内科で診療時間が短い・終了が早いと、来院のピークである16:30〜19:00の来院希望者を受け入れられず、社会人が受診しにくくなります。結果として、夕方の内視鏡(上部・下部)やポリープ切除(ポリペクトミー=内視鏡でポリープを取る処置)の予約が入れづらく、前処置との段取りも合わないため待機が長期化し、「すぐ診てもらえる他院」へ流れる人が増えます。さらに「いつ診察しているかわかりにくい」という印象が広がると紹介・口コミが鈍り、内視鏡機器機の稼働率が下がって固定費負担が重くなります。休診と早仕舞いが重なると初診・再診のフォローが途切れやすく、満足度・継続率・単価といったKPIも悪化。結果として、開院初期の集患スピードが落ち、投資回収と地域でのポジション確立が遅れます。
週10から9コマ以上は設定し、ピークである夕方〜夜間もしっかりと患者を受け入れられるようにしましょう。
専門コンサルタントが見た実際の成功事例
消化器内科クリニックを開業した40代後半の男性医師の事例です。
地域に溶け込む姿勢と堅実な診療で着実に信頼を築きました。開業の場所はスーパー併設の医療モールで、競合も少なく、地域住民にとってアクセスのよい環境に恵まれていました。
当初は内視鏡検査を積極的に行わず、一般診療を中心にスタートしました。コロナ禍という困難な状況の中でも、患者をできる限り診察し、日曜日にはワクチン接種の場を設けるなど、地域のために尽力しました。この献身的な取り組みが口コミで広がり、地域医療への信頼は厚くなっていきました。
その後、内視鏡検査を徐々に導入し、診療の幅を広げました。内視鏡は利益を生み、経営の安定に寄与しましたが、医師自身は「技術だけに頼るのではなく、丁寧な診療こそが大切」と考えていました。実際、内視鏡の技術が優れていても、それを前面に押し出すだけでは成功につながらないケースは多いと感じています。
医師は患者一人ひとりに丁寧に向き合う姿勢を貫いています。その真摯な態度は「気になる症状があればまずこの先生に相談したい」と思わせ、健診後のフォロー、肺がん検診や肺炎球菌ワクチン接種など、さまざまな医療ニーズを受け止める基盤となりました。
他のクリニックの内覧会にも頻繁に参加しています。通常では考えられないほど遠方にも顔を出し、私自身も驚いたほどでした。クリニックの内装といった細部にはこだわりすぎず、華美な演出も避けましたが、何か取り入れる参考になることはないかと、力を注ぐ姿勢が印象的でした。
現在では地域の「安心して頼れる消化器内科」として安定した経営を実現しています。常に穏やかな笑顔を絶やさず、過度に主張することなく、必要な医療を確実に提供し続けていることが、成功の最大の要因となりました。誠実さと地域貢献を重んじたこのクリニックは、消化器内科開業のひとつの理想的な成功例といえるでしょう。
まとめ
消化器内科クリニックの開業においては、他診療科と比較して高い開業資金が必要です。一般的には50坪程度の面積が必要とされ、一般的に必要とされる機器を揃えると開業資金は1億2,000万円を越えてきます。高額な内視鏡検査機器を複数導入する場合においては、開業資金はさらに膨れ上がります。消化器内科に限らず、近年では、内装工事費や医療機器の価格が高騰していることから、これから開業しようと考えている場合には今後のさらなる価格上昇も見越した資金計画が必要でしょう。
自己資金の目安は、一般的には開業に必要な総資金の約10%程度ですが、開業資金の大部分は金融機関からの事業融資を活用するのが一般的な資金調達の方法です。開業準備では、「どのタイミングで、どの支出が、どのくらい必要になるか」をあらかじめ明確にし、自己資金をどう使うかの計画を立てておくことが、安定したスタートを切るための鍵となります。
消化器内科の開業においては、利便性や視認性の高さ、競合の数などの検討はもちろんのこと、比較的生活に余裕があり、保険診療外の検査を定期的に実施しているような方が多いエリアを選定することもポイントとなります。さらに、検査だけではなく一般内科診療にも力を入れて地域住民の健康を守るというスタンスを持つことで自ずと集患が進み、クリニック開業の成功につながるでしょう。
この記事を書いた人:田中秀直
プラザ薬局医院開業担当。
医療器機ディーラーで17年勤務後、ドクターの開業コンサルティング業務に従事。
医療モールの組成も行うようになり、内科4名、皮膚科2名、小児科4名、整形外科4名、心療内科2名、
継承開業にて内科2名の開業支援実績がある。
プラザ薬局では、医療モールの組成、クリニック誘致、クリニック運営サポートなど幅広く業務を担当しており、
豊富な開業支援実績の経験を活かし、クライアント様から厚い信頼を得ている。